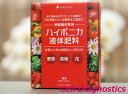ヒヤシンスの育て方…葉や茎が伸び過ぎたら支柱を立てるか、それがダメなら…

目次
ヒヤシンスの特徴は?茎や葉が伸び過ぎた場合は?
水やり
肥料
管理場所
球根の植え付け
病害虫
学名などの基礎データ
 最終更新
最終更新- 植物名
- ヒヤシンス
- 科名
- キジカクシ科
- 属名
- ヒヤシンス属
- 学名
- Hyacinthus
- 別名
- ヒアシンス
- 耐寒
- マイナス10度
- 水やり
- 水控え目
- 場所
- 外の日なた
- 難易度
- 中級者向け
スポンサーリンク
ヒヤシンスの特徴は?

一般的には球根を植えるのではなくて、植わった鉢を12月~3月にかけて買ってくることが多いです。永く楽しむコツとしては、花が傷んだら、その花ガラを小まめに摘むことです。花ガラを放置しておくと、その花に種を作ろうと栄養が回ってしまい、他の花の持ちが悪くなったり、つぼみが咲きづらくなるということがあります。これは他の植物でも同じです。
とても甘い香りがするので、嬉しいのですが、匂いにつられて蜂が寄ってくることがありますので、窓辺に置くときは気をつけてください。
水耕栽培については
を参考にしてください。
スポンサーリンク
茎や葉が伸び過ぎた場合は?
ヒヤシンスは室温・気温が高いとニョキニョキ伸びてしまいます。茎が伸びすぎたときは、支柱を立ててやるといいのですが、球根をいためるかもしれませんので、丁寧に支柱をするか、鉢をもっと大きな重い鉢に中に入れて管理します(二重鉢)。不恰好ですがしょうがない。葉っぱはだらしないですが、切らずに残しておきます。というのも葉っぱで光合成し、来年の栄養を球根に蓄えているからです。来年咲かせないなら、多少、切り取ってもいいです。
あと、とにかくもっと涼しいところに移動させましょう。じゃないと更に徒長してしまいますよ。
特に水耕栽培のときに茎が伸びすぎると器ごとひっくり返ることもあります。そのときは土植えに植え替えた方が無難です。
水やり
9月~4月くらいまでの生育期の間は、土の表面が乾いたらタップリと水を与えてください。来年も咲かせようと思うのであれば、花が枯れたら、水やりを減らし、6月の梅雨になる前に掘り起こして日陰の風通しのいい場所に放置しておきます。また9月に植えつけてください。
肥料
花が咲いている場合は、10日に1回液肥をやるか、一ヶ月に一回化成肥料を周囲にまきます。気温が上がってくる5月以降は葉っぱは残って球根を太らせて来年の栄養を貯めているんですが、この時期に肥料をやると夏に球根が腐る要因になるので、開花が終わったら、固形の肥料ではなくて、通常の倍に薄めた液体肥料に切り替えて、葉っぱが緑のうちは球根を太らせましょう。もしくは追肥は一切ストップします。
管理場所
ヒヤシンスは日光を好みます。室内で観賞する場合でも出来るだけ明るい場所で管理します。室内で管理すると暖か過ぎてすぐに花が開きますので、できれば戸外の日当たりで管理します。日当たりの悪いところで栽培すると花が減り、徒長して不恰好になりますし、球根が太らず来年の開花が鈍くなります。日当たりで管理しましょう。
気温が高いと花がすぐ開きます

花がしぼんでしまったら戸外の日当たりの寒い(涼しい)所で管理して、春になったら土に植えてください。霜にあたっても大丈夫です。
花が終わったら?
花が終わったら、花茎の根元から切ってしまいます。戸外の日当たりに置いていると新しい花芽が上がってきてもう一度開花することがあります。開花が終わったら、葉っぱが枯れるまでは日光に当てて、肥料をやり、葉っぱが黄色くなったら掘り上げて保存しておきます。
球根の植え付け
9月に球根を、一般的な培養土で植えます。地植えの場合は、石灰で中和してから腐葉土か堆肥を入れて土を作って植えます。鉢植えは鉢底の穴を鉢底ネットで塞いで鉢底石を2cm〜3cm入れて球根を植えます。球根の頭が少し出るように植えます。
庭上の場合は深さ30cmを掘って苦土石灰で中和してから、1週間待って、腐葉土を2割足して化成肥料を入れて混ぜて、株間10cm空け、球根の頭が深さ5cm〜10cmになるように植えます。最後にしっかりと水をやります。
病害虫
ヒヤシンスが活動する冬〜春は寒くて病害虫はほとんど見られないですが、根ダニ、アブラムシ、ナメクジなどがたまに見られます。問題になるのは夏の多湿による腐敗です。スポンサーリンク