12月のラベンダーの栽培
スポンサーリンク
12月のラベンダーの栽培
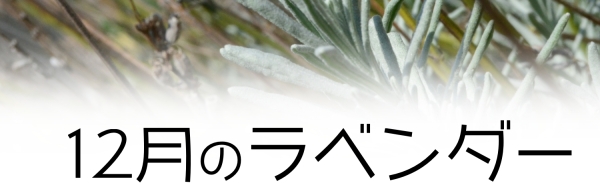
栽培のまとめ
●水はやり過ぎない。土が乾いてから数日経って水をやる程度。
●寒風が株元に当たると乾燥し過ぎてしまうし、土が凍結するので、マルチングをする。
●マルチングは庭植えも鉢植えもする。室内で管理するときもマルチングした方がいい。
●寒さに弱い品種は室内へ。中でもプテロストエカス系は必ず室内へ。
●植え替え・植え付けをする場合は土を落とさず、根を傷つけないようにします。
●寒風が株元に当たると乾燥し過ぎてしまうし、土が凍結するので、マルチングをする。
●マルチングは庭植えも鉢植えもする。室内で管理するときもマルチングした方がいい。
●寒さに弱い品種は室内へ。中でもプテロストエカス系は必ず室内へ。
●植え替え・植え付けをする場合は土を落とさず、根を傷つけないようにします。
スポンサーリンク
水やり
庭植えの水やり
自然に降る雨だけで十分です。水やりはしません。鉢植えの水やり
寒さで根の動きが止まっていますので、水やりは減らします。土が乾いて数日経って水をやるようにします。土の表面が乾いていても、内部に水が残っていることが多いので、持ち上げて重さで判断するか、できれば土壌水分計で計測してから水やりをするといいです。葉っぱの汚れ
葉っぱに埃・汚れがついている場合は、晴れた日の午前中に葉っぱに水をかけて洗い流してあげてください。これは葉っぱの中の精油と埃がくっついている状態で、そのままにしていると葉っぱの呼吸をする穴の気孔(キコウ)を塞いで枯れてしまいます。●葉っぱが寒さに当たると赤紫になります。これは寒さで紅葉しているのと同じなので問題はないです。
肥料
肥料はやりません。根の動きが止まっているので肥料をやると根が肥料で傷んでしまいます。植え付け・植えかえ
寒冷地でなければ植え替えや、庭植えや、庭植えしたものを鉢植えに鉢上げすることもできますが、根を傷つけてはいけません。ダメージを取り返すことが出来ませんから、植え付け・植え替えをするときには土を落とさないようにします。管理場所・日当たり
日当たりが良いのが理想
日当たりがいい、寒風の当たらない場所で管理します。寒風は乾燥していて、寒風がラベンダーの株元を直撃すると極端に乾燥しますし、土が凍ってしまいますから、株元に必ずマルチングをします。室内で管理する系統
ラベンダーは系統によって耐寒温度が違います。プテロストエカス系は0度か5度あたりで枯れるので冬は室内で管理します。ストエカス系・デンタータ系はマイナス5度を下回ると枯れます。マイナス5度というのは土が凍結する温度です。冬に土が凍結する地域では室内に取り込んで管理します。アングスティフォリア系は寒さに強いので、戸外で管理しましょう。室内での管理
室内の日当たりで管理します。昼間に人が生活していて昼(夕方)に暖房(20度とか)がかかっている場合は、暖房の暖かさが残っていて明け方の一番寒くなるときでも5度以下になることはほぼないです(家の構造にもよるけど)。ただし、窓の近くは外気が近いから寒波が来ると、夜中に氷点下以下になることがあるので、寒波が来たときなどは室内の中央へ移動させます。
最低最高温度計という最高気温と最低気温を図る温度計があります。これで計測して夜中の温度を推測しておくといいです。1500円くらいであります。
マルチング
マルチングは11月にしておきたいです。まだマルチングしていないならば12月にやりましょう。腐葉土やバークチップを株元に敷き詰めて、株元の乾燥と凍結を防ぎます。庭植えだけでなく、鉢植えでもやります。室内で管理する場合も乾燥対策でマルチングをした方がいいです。●寒さに強いアングスティフォリア系やラバンディン系でもマルチングはする。乾燥対策であり、凍結・霜柱対策でもあるので。
●アングスティフォリア系やラバンディン系でも霜柱や凍結で枯れる。寒さに強いというのは気温だけ。
●雪が積もると、雪が保温になって地表近くのは0度くらいになります。実は雪が積もる方がラベンダーにとっては暖かいです。雪が積もらない地域の方が寒風が株元に当たって霜柱・凍結して枯れやすい。
●アングスティフォリア系やラバンディン系でも霜柱や凍結で枯れる。寒さに強いというのは気温だけ。
●雪が積もると、雪が保温になって地表近くのは0度くらいになります。実は雪が積もる方がラベンダーにとっては暖かいです。雪が積もらない地域の方が寒風が株元に当たって霜柱・凍結して枯れやすい。
風除け
強い寒風(北風)が吹くと、乾燥もしますが、強風で株が揺らされて、根元がグラグラになって土から露出して枯れることがあります。吹きさらしにならないように、近くに風除けを設置します。強剪定
暖地・中間地はアングスティフォリア系とラバンディン系の強剪定をしましょう。ラベンダーは古い枝をそのままにしておくと、株全体が老化してきて、生育に勢いがなくなります。そこで2年に一回程度、株全体を半分ほどに切り戻します。12月はアングスティフォリア・ラバンディン系の強剪定の時期です。梅雨前にやるのは風通しをよくするもので、こちらは株のリフレッシュです。
木質化した部分が増えたら、やるような感じですね。
具体的な強剪定
株元を見て、木質化したところから新芽が出ているなら、その新芽が出ているところのチョイ上までをバッサリと切り戻します。これで枝が更新されて元気になります。全く、新芽が出ていない枝もありますが、これはもう老いているので根元から切り落としてしまいます。終わるとほぼ「丸坊主」になります。
強剪定の時期は種類と地域によって違うので詳細は以下のリンクを参考にしてください。
最後に
先月の育て方はを参考に。
来月以降は
を参考にしてください。
スポンサーリンク







